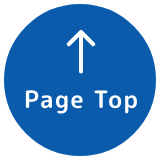NTM(非結核性抗酸菌症)外来Clinical Department
NTM(非結核性抗酸菌症)外来
概要
細菌のうち抗酸菌属に分類されるものに結核菌、非結核性抗酸菌やライ菌があり、結核菌や非結核性抗酸菌による感染症を抗酸菌症と言います。
肺結核
結核菌が肺に感染して起こる病気です。肺結核を発病するとせき、痰、血痰、だるさ、発熱、寝汗、体重減少などが出ることもありますが、無症状のこともあります。結核菌は人に寄生する菌で環境中では生存できないため、結核を発病している人がせきをしたときに出る結核菌を含んだ細かいしぶきを通して人から人に感染します。そのためせき、痰が出る場合、他人にうつる可能性が高くなります。痰の中の結核菌が少なければ外来治療が可能ですが、結核菌が痰から大量に出ている場合には他人にうつらないよう、菌が減ってくるまで結核専門施設で入院治療を要します。結核と診断されたら、抗結核薬の内服治療をします。標準治療は6ヶ月間と長いですが、途中でやめて治療が中途半端になると薬剤耐性結核となり薬が効かなくなってしまうため、最後までしっかり治療することが大切です。当院では肺結核の診断と外来治療を行っています。他人にうつる可能性がある病状と判断した場合は入院治療ができる結核専門施設へご紹介させていただきます。
肺非結核性抗酸菌症
非結核性抗酸菌が肺に感染して起こる病気です。非結核性抗酸菌とは結核菌とライ菌以外の抗酸菌の総称で、土や水などの自然環境中に広く生息し現在150菌種以上が発見されています。菌を含んだ埃や水滴を吸入することにより感染すると推定されており、感染するとせき、痰、血痰、だるさ、発熱、寝汗、体重減少などが出ることもありますが、無症状のことも多くあります。多くは数年から10年以上かけてゆっくりと進行します。肺非結核性抗酸菌症は他人にうつることはないため、外来治療を行います。
治療は数種類の抗菌薬を数年にわたって服用する薬物療法や、病変が限局していれば手術療法などがあります。非結核性肺抗酸菌症の7〜8割ぐらいはMAC(Mycobacterium-avium complex)と呼ばれる菌で占められ、次に多いのがM.kansasiiです。
菌種や病状、また基礎疾患などで治療方針が異なるため、まずは受診し検査や治療についてご相談ください。国内外のガイドラインを重視し、内服、注射、アミカシン吸引などの薬物治療やリハビリ、栄養まで含めた包括的な介入を心がけます。喀血の場合はIVR(カテーテルを用いた止血術)を要することがあり、近隣の医療機関と連携を行います。
水堂 祐広 (すいどう よしひろ)

| 役職 | 内科部長 |
|---|---|
| 専門分野 | 呼吸器、感染症、医療政策 |
| 出身大学 | 千葉大学、国際医療福祉大学 大学院 |
| 資格 | 医療ビジネス経営学修士(h-MBA) 日本内科学会 総合内科専門医 日本呼吸器学会 専門医 日本感染症学会 専門医、指導医 日本化学療法学会 抗菌化学療法指導医 日本結核病学会 結核・抗酸菌症指導医 日本エイズ学会認定医 日本がん治療認定機構 がん治療認定医 JMECCコースインストラクター インフェクションコントロールドクター ICLSコースディレクター 身体障害者福祉法第15条指定医(呼吸器、免疫) 川崎市難病指定医 医療情報技師 聖マリアンナ医科大学 非常勤講師 |
| 一言メッセージ | 院内外の各職種の方々と協力し、地域の皆さんに持続可能な医療を提供できるよう心がけます。 |
受診について
診療科のご案内
診療科
専門外来
- スポーツ整形外科
- 脊椎脊髄病センター
- 内視鏡センター
- 人工透析センター
- もの忘れ外来
- 頭痛外来
- 人工関節センター(麻生リハビリ総合病院)
- 消化器センター
- 気管支喘息外来
- NTM(非結核性抗酸菌症)外来
部門
診療支援チーム